今回のひとりごとは 私が会社を辞めた話です
私が61歳と8ヶ月で会社を退職した理由
私が勤めていた会社は60歳が定年で その後5年間は再雇用という形で毎年更新できるシステムでした
60歳の定年と同時に役職が無くなります
いわゆる役職手当が無くなり収入が減ります
さらに基本給も減額するシステムでしたので
年収がガクッと減るという現実を味わいながら1年間仕事を続けていました
私としては 役職が無くなり収入も減るのだから 当然仕事量は減り責任も減ると思っていたので
実際の仕事でも 役職者が行うべき仕事が回って来たときは
「いや それ俺の仕事じゃない」と断っていました
自分としてはいろいろ不満がありながらも 我慢して再雇用を続けるつもりでした
61歳となり2回目の更新の時に
会社側から言われたのは「あなたは能力があるのだから出来ることは何でもやってください」
いやいや それはおかしい 納得できない
「それなら会社を辞めさせていただきます」と告げました
出来ることを何でもやるということは 今までと同じ仕事をするということになる
それなら 今までと同じ給料を貰わないと納得できない
これが私の考え方でした
それから 話し合いというか 引き止めというか
いろいろ有り 8ヶ月後に退職となりました
会社側の要望を受け入れて再雇用を続けている人が
何人もいるということが私には信じられません
「老害」という言葉があります
企業で 年齢や経験を盾に実権を握り続ける老人や
周囲の人の意見を聞かず迷惑をかける高齢者のことを指します
きっと会社に何を言われても辞めない人にこのタイプが多いのではないかと
私は思います(全員がそうだと言ってるわけではありません)
考え方には賛否あるとは思いますが 私の人生なので批判は受けません
サラリーマンであればいつかはやってくる定年退職
それに向けて参考になればと思います

ここからは シニアの労働のあり方 定年制の課題について思うことを綴ってみました
シニアの労働と定年制の課題
少子高齢化が進む日本では、労働力不足が深刻な問題となっています。
政府もシニア層の活用を推進し、働き続けたい高齢者に向けた政策を強化していますが
日本には根強く「定年制」と「年齢による賃金カット」というシステムが生き残ってます
これは高齢者が持つ豊富な経験や専門知識を、無駄にするものになっていて
見直をする必要がると思います。
定年制と賃金カットの問題点
欧米では、個人の成果によって評価される仕組みが確立されており、
年齢による賃金の一律カットは一般的ではありません。
能力や実績に基づいた評価システムが主流であり、
年齢に関係なく優れた人材が適切に評価される土壌があります。
一方で、日本や韓国では、一定の年齢を迎えると
賃金が大幅に減少する仕組みが長年維持されています。
多くの企業では60歳の定年後、再雇用されても
給与が30〜40%も削減されるケースが珍しくありません。
企業側の視点から見ると、
高齢者の給与水準を下げることで人件費の負担を軽減できるというメリットがありますが
労働者にとっては不公平なシステムとも言えます。
特に問題なのは、この賃金カットが個人の能力や業績に関係なく
年齢のみを基準に行われることです。
同じ仕事内容であっても、定年前後で大幅に報酬が下がることは
シニア労働者のモチベーション低下を招き、結果的に生産性の低下にもつながりかねません。
現実との乖離
定年制の導入背景には、日本の年功序列制度が大きく影響しています。
年功序列では、勤続年数が長いほど給与が上昇するため、定年近くになると人件費が膨らみます。
そのため、多くの企業は定年制を維持することで、高齢者の労働コストを削減しようとしています。
しかし、現在の日本社会では、健康寿命の延伸により、
60歳を超えても十分に働ける人が増えています。
厚生労働省の調査によれば、65〜69歳の就業率は年々上昇し、
2023年には約50%に達しています。
多くのシニアが意欲と能力を持ちながらも、定年制によって
本来の力を発揮できない状況が生じているのです。
さらに、年金支給開始年齢の引き上げも相まって、
経済的な理由から働き続ける必要があるシニアも増加しています。
定年制が現実に即していないため、
多くのシニアが低賃金で再雇用されるという矛盾が生じています。
海外の事例から学ぶ
アメリカやEU諸国では、年齢差別禁止法が厳格に施行されており、
年齢を理由とした不利益な扱いは法的に認められていません。
例えば、アメリカでは「雇用における年齢差別禁止法(ADEA)」により、
40歳以上の労働者に対する年齢差別が禁止されています。
ドイツやフランスなどでは、段階的な退職制度や柔軟な勤務形態を導入し、
シニア労働者が自身の能力や希望に合わせて働ける環境が整備されています。
特にドイツでは、部分退職制度(Altersteilzeit)により、
労働時間を徐々に減らしながら、若手への知識や技術の継承を行う仕組みが確立されています。
このような海外の取り組みは、日本の雇用システム改革に多くの示唆を与えています。
年齢ではなく、能力や成果に基づいた評価システムへの移行が、
シニア層の労働意欲向上と企業の競争力強化につながる可能性があります。
これからのシニア雇用のあり方
今後、日本の労働市場が持続可能であるためには、
成果主義の導入や柔軟な雇用形態の促進が求められます。
欧米のように、年齢ではなく能力や実績に基づいて評価されるシステムを構築することで、
シニア層の労働意欲を高めることができるのではないでしょうか
また、企業側もシニアの経験やスキルを有効活用するために、
働き方の多様化を進める必要があります。
長年培ってきた専門知識や人脈、判断力などは、企業にとって貴重な資産です。
これらを最大限に活用できる仕組みづくりが、企業の持続的な成長にも寄与するでしょう。
定年退職に向けての準備
そうは言っても「定年制」と「年齢による賃金カット」というシステムが
簡単に変わるわけがありません
もうすぐ定年を迎える世代の人にとっては 差し迫った問題となります
ぜひ 会社の言いなりにならないように 今から準備をしていただきたいと思います
具体的には 収入が減っても困らない貯蓄を準備する
納得できなかったら 我慢しないでいられるように 次をスキルを準備しておく
又は辞めても大丈夫な貯蓄を準備しておく
10年あれば充分準備できます
そんなに無いという人も2〜3年あればある程度準備できます
全然遅くないです 準備していただきたいと思います
関連記事:定年退職の準備は固定費の見直しから始める 生活費の節約は家庭菜園できゅうりを育てる
・定年退職から10ヶ月、収入がなくても暮らせる?自由な生活とお金のリアル
・老後の家計簿事情|平均毎月3万円赤字!? 年金だけで暮らせる?

おわりに
少子高齢化による労働力不足が進む中、シニアが適正な評価を受けながら
働ける環境を整えることが、日本社会全体の持続的な成長につながるのではないでしょうか。
シニアの豊富な経験と若者の新しい発想が融合することで、
より創造的で活力ある社会が構築されることを期待します。
にほんブログ村
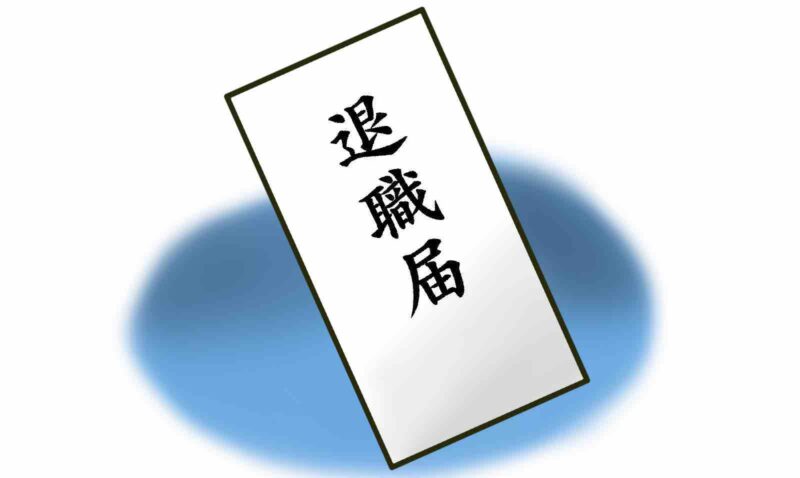


コメント