2018年9月6日午前3時7分、北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度7の大地震が発生しました。厚真町では大規模な土砂崩れが起き、道内では死者44人、負傷者780人以上という大きな被害が出ました。
そして、この地震を語る上で外せないのが、北海道電力管内全域で発生した「ブラックアウト」――全域停電です。広大な北海道が一斉に電気を失い、道内の生活機能が停止したあの瞬間を、今も鮮明に覚えています。
地震発生の瞬間と出勤
私は地震の揺れと同時に飛び起きました。地震の時にはビル設備の復旧にあたる仕事をしていたため、真っ先に頭に浮かんだのは「会社に行かなければ」ということでした。
発生直後は電気は点いており、テレビで地震の情報も確認できたと記憶しております。
数分後には電気が消え、情報はスマホのみとなりました。
外に出ると、街はすでに停電で真っ暗。
信号も消え、車もほとんど走っていない異様な静けさの中、会社へ向かいました。
人も車もいない真っ暗な道を走る体験は、便利さではなく不気味さと不安を強く印象づけました。
まるでゴーストタウンを走っているような錯覚を覚えました。

停電下でのもどかしい時間
初日はまず被害状況を把握し、そこから復旧作業を始める予定でした。
しかし全道停電の影響で作業がまったく進められず、実際に動き出せるまでには時間がかかりました。ビル設備の復旧作業を担う立場でありながら、電気が戻らなければ何もできない。
この無力感と焦燥感は、今でも忘れられません。
そこから2日間ほどは、何もできず、停電の復旧待ち、街中は信号も消え、コンビニやスーパーの棚もすぐに空になり、人々の不安がそのまま風景として広がっていました。
社会全体が機能を失った状態は、まさに「都市が止まった」光景でした。
夜に信号もなく、人も車もほとんどいない状態で車で走ると、普段なら1時間ほどかかる距離が、その夜はわずか30分ほどで到着することができました。
通信の途絶とデマの拡散
地震直後は携帯電話が使えたものの、時間の経過とともに電波が弱まり、やがてほとんど繋がらなくなりました。
情報が入らないというのは、想像以上に不安を募らせるものでした。
災害時には正確な情報が命綱だと痛感した瞬間です。
さらに当時は、確かな情報が限られていたこともあり、根拠のない噂やデマが飛び交いました。
「数時間後に大規模な断水が始まる」「本震が数時間後に来る」というような話が広がり、人々の不安を増幅させていました。
実際には確認されていない情報でも、停電や通信障害で正しいニュースが届かない中では信じてしまう人も多く、デマがいかに人の心を揺さぶるかを目の当たりにしました。
この経験から、災害時には「信頼できる情報源を確認すること」が何より大切だと痛感しました。
SNSや人づての噂に左右されるのではなく、自治体や公共機関の公式発表を冷静に受け取る姿勢が必要だと思います。

燃料不足と補給部隊
追い打ちをかけたのがガソリン不足です。
市内のガソリンスタンドはすべて閉鎖され、燃料補給の手段がなくなりました。
復旧作業に向かうにもガソリンがなければ動けません。
そこで私たちは携行缶を大量に購入し、水力発電の普及により停電していなかった旭川まで燃料を買いに行く「補給部隊」を編成しました。
札幌のような大都市で、燃料を求めて遠征するなど、誰も想像していなかったはずです。

復旧への道のり
電気が復旧せず、暗い状態のままでも営業していた、コンビニやラーメン店には頭が下がる思いでした。
3日目あたりから徐々に停電が解消され、ようやく本格的に復旧作業にあたることができました。
完全に落ち着くまでには体感で1週間ほどかかりました。
暗闇の街に少しずつ明かりが戻り、人々の生活が再び動き出す光景は、今でも強く心に残っています。復旧の現場に立ちながら、自分自身も被災者であるという複雑な感情を抱いた数日間でした。
あの時から得た教訓
北海道胆振東部地震で私が痛感したのは、「当たり前の生活は本当に脆い」ということです。
電気が止まるだけで、通信も物流も生活も一瞬で麻痺します。
さらに燃料不足や情報断絶が重なれば、都市であっても簡単に孤立するのだと学びました。
この経験以来、私は災害に備えて以下のことを心がけています。
- 数日分の水・食料の備蓄を常に確保する
- モバイルバッテリーや携帯ラジオを用意しておく
- 車のガソリンは常に半分以上を保つ
- 家族や知人と、災害時の連絡手段を確認しておく
備えは「余計なもの」ではなく、「日常を守る最低限の保険」であると、あの時強く実感しました。
この地震が9月という気候が良い時だったことが幸いしたと思います、これが冬のマイナス10℃を下回るような時だったらと思うとゾッとします。電気が無くても使える暖房器具を一つは用意しておきましょう。
結びに
2018年9月6日の胆振東部地震から、もう7年が経ちました。
しかし、あの日の暗闇、静まり返った街、そして少しずつ明かりが戻っていく光景は、今も心に焼き付いています。
あの経験を風化させず、次の災害への教訓とすることが、実際に体験した者としての務めだと思っています。
この記事を読んでくださった方にも、ぜひ一度ご家庭の備蓄や防災対策を点検していただければ幸いです。
「備えあれば憂いなし」――あの大停電を経験した北海道の住民として、心からそうお伝えしたいです。
この記事が気に入っていただけましたら、ぜひブログのブックマークとSNSシェア・フォロー・Xでリポスト 下記のブログ村で投票をお願いします。
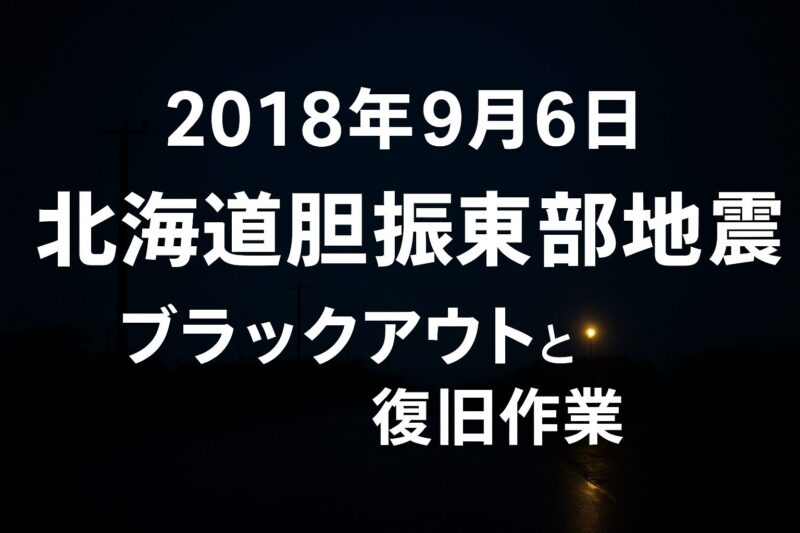
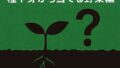
コメント